�z�[�� >> ���\�ٌ�����W���̏Љ� >> ���\�ٌ����� >> �ߘa6�N1��������3���� >>�i�ߘa6�N3��6���ٌ��j >>�ʎ�2�@�W�@�ߓ�
�ʎ�2�@�W�@�ߓ�
1�@�����Ŗ@
�����Ŗ@��22���s�]���̌����t�́A���@��R�́s���Y�̕]���t�œ��ʂ̒�߂̂�����̂������ق��A�������͈②�ɂ��擾�������Y�̉��z�́A���Y���Y�̎擾�̎��ɂ����鎞���ɂ��|�K�肵�Ă���B
2�@���Y�]����{�ʒB
(1)�@���Y�]����{�ʒB�i���a39�N�S��25���t����56�ق����Œ������ʒB�B�ȉ��u�]���ʒB�v�Ƃ����B�j�P�s�]���̌����t��(2)�́A���Y�̉��z�́A�����ɂ����̂Ƃ��A�����Ƃ́A�ېŎ����ɂ����āA���ꂼ��̍��Y�̌����ɉ����A�s���葽���̓����ҊԂŎ��R�Ȏ�����s����ꍇ�ɒʏ퐬������ƔF�߂��鉿�z�������A���̉��z�́A���̒ʒB�̒�߂ɂ���ĕ]���������z�ɂ��|��߂Ă���B
(2)�@�]���ʒB�T�s�]�����@�̒�߂̂Ȃ����Y�̕]���t�́A�]���ʒB�ɕ]�����@�̒�߂̂Ȃ����Y�̉��z�́A���̒ʒB�ɒ�߂�]�����@�ɏ����ĕ]������|��߂Ă���B
(3)�@�]���ʒB�U�s���̒ʒB�̒�߂ɂ���ꍇ�̕]���t�́A�]���ʒB�̒�߂ɂ���ĕ]�����邱�Ƃ��������s�K���ƔF�߂�����Y�̉��z�́A���Œ������̎w�����ĕ]������|��߂Ă���B
(4)�@�]���ʒB20�|�Q�s�n�ϋK�͂̑傫�ȑ�n�̕]���t�i�ȉ��u�{���ʒB�v�Ƃ����B�j�́A�n�ϋK�͂̑傫�ȑ�n�i�O��s�s���ɂ����Ă�500![]() �ȏ�̒n�ς̑�n�A����ȊO�̒n��ɂ����ẮA1,000
�ȏ�̒n�ς̑�n�A����ȊO�̒n��ɂ����ẮA1,000![]() �ȏ�̒n�ς̑�n�������A���̃C����n�܂ł̂����ꂩ�ɊY��������̂������B�ȉ��u�n�ϋK�͂̑傫�ȑ�n�v�Ƃ����B�j�ŁA�]���ʒB14�\�Q�s�n��t�ɒ�߂�n��i�ȉ��u�n��敪�v�Ƃ����B�j�̂����A���ʏ��ƁE���p�Z��n��y�ѕ��ʏZ��n��Ƃ��Ē�߂�ꂽ�n��ɏ��݂�����̂̉��z�́A�]���ʒB15�s���s���i��t����]���ʒB20�s�s���`�n�̕]���t�܂ł̒�߂ɂ��v�Z�������z�ɁA���̑�n�̒n�ς̋K�͂ɉ����A���̎Z���ɂ�苁�߂��K�͊i��������悶�Čv�Z�������z�ɂ���ĕ]������|��߂Ă���B
�ȏ�̒n�ς̑�n�������A���̃C����n�܂ł̂����ꂩ�ɊY��������̂������B�ȉ��u�n�ϋK�͂̑傫�ȑ�n�v�Ƃ����B�j�ŁA�]���ʒB14�\�Q�s�n��t�ɒ�߂�n��i�ȉ��u�n��敪�v�Ƃ����B�j�̂����A���ʏ��ƁE���p�Z��n��y�ѕ��ʏZ��n��Ƃ��Ē�߂�ꂽ�n��ɏ��݂�����̂̉��z�́A�]���ʒB15�s���s���i��t����]���ʒB20�s�s���`�n�̕]���t�܂ł̒�߂ɂ��v�Z�������z�ɁA���̑�n�̒n�ς̋K�͂ɉ����A���̎Z���ɂ�苁�߂��K�͊i��������悶�Čv�Z�������z�ɂ���ĕ]������|��߂Ă���B
�C�@�s�X���������i�s�s�v��@��34���10�����͑�11���̋K��Ɋ�Â���n�����ɌW�铯�@��S���s��`�t��12���ɋK�肷��J���s�ׁi�ȉ��A�P�Ɂu�J���s�ׁv�Ƃ����B�j���s�����Ƃ��ł�����������B�j�ɏ��݂����n
���@�s�s�v��@��W���s�n��n��t��P����P���ɋK�肷��H�Ɛ�p�n��ɏ��݂����n
�n�@�e�ϗ��i���z��@��52���s�e�ϗ��t��P���ɋK�肷�錚�z���̉��זʐς̕~�n�ʐςɑ��銄���������B�j��10����40�i�����s�̓��ʋ�ɂ����Ă�10����30�j�ȏ�̒n��ɏ��݂����n
�i�Z���j
![]()
��̎Z�����́u�a�v�y�сu�b�v�͒n�ϋK�͂̑傫�ȑ�n�����݂���n��ɉ����A���ꂼ�ꎟ�Ɍf����\�̂Ƃ���Ƃ���B
(�C)�@�O��s�s���ɏ��݂����n
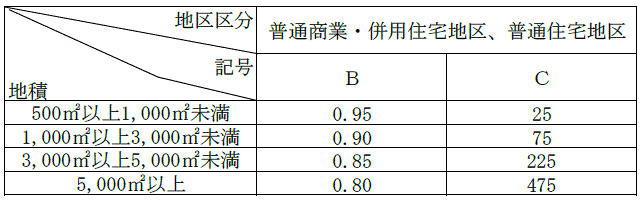
(��)�@�O��s�s���ȊO�̒n��ɏ��݂����n
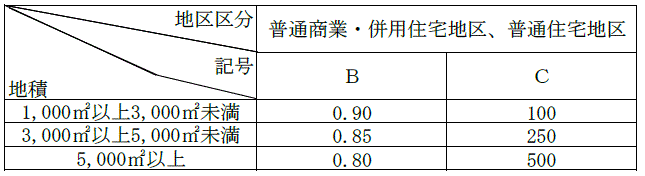
(��)1�@��L�Z���ɂ��v�Z�����K�͊i������͏����_�ȉ���Q�ʖ������̂Ă�B
2�@�u�O��s�s���v�Ƃ́A���̒n��������B
(1)�@��s�������@��Q���s��`�t��R���ɋK�肷������s�X�n���͓����S���ɋK�肷��ߍx�����n��
(2)�@�ߋE�������@��Q���s��`�t��R���ɋK�肷������s�s��斔�͓����S���ɋK�肷��ߍx�������
(3)�@�������J�������@��Q���s��`�t��R���ɋK�肷��s�s�������
(5)�@�]���ʒB21�|�Q�s�{�������ɂ��]���t�́A�{�������ɂ��]�������n�̉��z�́A���̑�n�̌Œ莑�Y�ŕ]���z�i�n���Ŗ@��381���s�Œ莑�Y�ېő䒠�̓o�^�����t�̋K��ɂ��y�n�ېő䒠���ɓo�^���ꂽ��N�x�̉��i���������B�ȉ������B�j�ɒn������̗ގ�����n�悲�ƂɁA���̒n��ɂ����n�̔������ቿ�z�A�������i�A�s���Y�Ӓ�m���ɂ��Ӓ�]���z�A���ʎ҈ӌ����i������Ƃ��č��ŋǒ��̒�߂�{�����悶�Čv�Z�������z�ɂ���ĕ]������|��߂Ă���B�������A�{�������ɂ��]������n��ɏ��݂���]���ʒB20�|�Q�ɒ�߂�n�ϋK�͂̑傫�ȑ�n�̉��z�ɂ��ẮA�{���{���̒�߂ɂ��]���������z���A���̑�n���W���I�ȊԌ������y�щ��s������L�����n�ł���Ƃ����ꍇ�̂P![]() ������̉��z��]���ʒB14�s�H�����t�ɒ�߂�H�����Ƃ��A���A���̑�n���]���ʒB14�\�Q�ɒ�߂镁�ʏZ��n��ɏ��݂�����̂Ƃ��ĕ]���ʒB20�|�Q�̒�߂ɏ����Čv�Z�������z������ꍇ�ɂ́A�]���ʒB20�|�Q�̒�߂ɏ����Čv�Z�������z�ɂ��]������|��߂Ă���B
������̉��z��]���ʒB14�s�H�����t�ɒ�߂�H�����Ƃ��A���A���̑�n���]���ʒB14�\�Q�ɒ�߂镁�ʏZ��n��ɏ��݂�����̂Ƃ��ĕ]���ʒB20�|�Q�̒�߂ɏ����Čv�Z�������z������ꍇ�ɂ́A�]���ʒB20�|�Q�̒�߂ɏ����Čv�Z�������z�ɂ��]������|��߂Ă���B
3�@�s�s�v��@��
(1)�@�s�s�v��@��S���12���́A�u�J���s�ׁv�Ƃ́A��Ƃ��Č��z���̌��z���͓���H�앨�̌��݂̗p�ɋ�����ړI�ōs���y�n�̋��`���̕ύX�������|�K�肵�Ă���B
(2)�@�s�s�v��@��V���s���敪�t��P���́A�s�s�v����i���@��T���s�s�s�v����t�̋K��ɂ��w�肳�ꂽ���������B�ȉ������B�j�ɂ��Ė������Ȏs�X����h�~���A�v��I�Ȏs�X����}�邽�ߕK�v������Ƃ��́A�s�s�v��ɁA�s�X�����Ǝs�X���������Ƃ̋敪�i�ȉ��u���敪�v�Ƃ����B�j���߂邱�Ƃ��ł���|�K�肵�Ă���B�܂��A���@��V���Q���́A�s�X�����́A���Ɏs�X�n���`�����Ă�����y�т����ނ�10�N�ȓ��ɗD��I���v��I�Ɏs�X����}��ׂ����Ƃ��A�����R���́A�s�X���������́A�s�X����}�����ׂ����Ƃ���|�K�肵�Ă���B
(3)�@�s�s�v��@��12���̂S�s�n��v�擙�t��P���́A�s�s�v����ɂ��ẮA�s�s�v��ɁA���Ɍf����v����߂邱�Ƃ��ł���|�K�肵�Ă���B�i��P���y�ё�T���̂ݔ����j
�C�@�n��v��i��P���j�i�ȉ��A�P�Ɂu�n��v��v�Ƃ����B�j
���@�W���n�搮���@�i���a62�N�@����63���j��T���s�W���n��v��t��P���̋K��ɂ��W���n��v��i��T���j�i�ȉ��A�P�Ɂu�W���n��v��v�Ƃ����B�j
(4)�@�s�s�v��@��12���̂T�s�n��v��t��P���́A�n��v��́A���z���̌��z�`�ԁA�����{�݂��̑��̎{�݂̔z�u������݂āA��̂Ƃ��Ă��ꂼ��̋��̓����ɂӂ��킵���ԗl��������ǍD�Ȋ��̊e�X������A�J�����A�y�ѕۑS���邽�߂̌v��Ƃ��A���̂����ꂩ�ɊY������y�n�̋��ɂ��Ē�߂���̂Ƃ���|�K�肵�Ă���B
�C�@�p�r�n�悪��߂��Ă���y�n�̋��i��P���j
���@�p�r�n�悪��߂��Ă��Ȃ��y�n�̋��̂������̂����ꂩ�ɊY��������́i��Q���j
(�C)�@�Z��s�X�n�̊J�����̑����z���Ⴕ���͂��̕~�n�̐����Ɋւ��鎖�Ƃ��s����A���͍s��ꂽ�y�n�̋��
(��)�@���z���̌��z���͂��̕~�n�̑������������ɍs���A���͍s����ƌ����܂����̓y�n�̋��ŁA�����{�݂̐����̏A�y�n���p�̓���������݂ĕs�ǂȊX��̊����`������邨���ꂪ�������
(�n)�@���S�ȏZ��s�X�n�ɂ�����ǍD�ȋ��Z�����̑��D�ꂽ�X��̊����`������Ă���y�n�̋��
(5)�@�s�s�v��@��34���i�ߘa�Q�N�@����43���ɂ������O�̂��́B�ȉ������B�j�́A���@��33���s�J�����̊�t�̋K��ɂ�����炸�A�s�X���������ɌW��J���s�ׂɂ��ẮA���Y�\���ɌW��J���s�y�т��̐\���̎葱�������ɒ�߂�v���ɊY������ق��A���Y�\���ɌW��J���s�ׂ����@��34���e���̂����ꂩ�ɊY������ƔF�߂�ꍇ�łȂ���A�s���{���m���́A�J���������Ă͂Ȃ�Ȃ��|�K�肵�Ă���B�i��10�������12���܂ŋy�ё�14���̂ݔ����j
�C�@�n��v�斔�͏W���n��v��̋����ɂ����āA���Y�n��v�斔�͏W���n��v��ɒ�߂�ꂽ���e�ɓK�����錚�z�����͑������H�앨�̌��z���͌��݂̗p�ɋ�����ړI�ōs���J���s�ׁi��10���j
���@�s�X�����ɗאڂ��A���͋ߐڂ��A���A���R�I�Љ�I����������s�X�����ƈ�̓I�ȓ��퐶�������\�����Ă���ƔF�߂���n��ł����Ă����ނ�50�ȏ�̌��z���i�s�X�������ɑ�������̂��܂ށB�j���A���Ă���n��̂����A���߂Œ�߂��ɏ]���A�s���{�����̏��Ŏw�肷��y�n�̋��i�ȉ��u���w����v�Ƃ����B�j���ɂ����čs���J���s�ׂŁA�\�茚�z�����̗p�r���A�J�����y�т��̎��ӂ̒n��ɂ�������̕ۑS��x�Ⴊ����ƔF�߂���p�r�Ƃ��ēs���{�����̏��Œ�߂���̂ɊY�����Ȃ����́i��11���j
�n�@�J�����̎��ӂɂ�����s�X���𑣐i���邨���ꂪ�Ȃ��ƔF�߂��A���A�s�X�������ɂ����čs�����Ƃ�����͒������s�K���ƔF�߂���J���s�ׂƂ��āA���߂Œ�߂��ɏ]���A�s���{�����̏��ŋ��A�ړI���͗\�茚�z�����̗p�r�������߂�ꂽ���́i��12���j
�j�@�s�s�v��@��34���P�������13���Ɍf������̂̂ق��A�s���{���m�����J���R����̋c���o�āA�J�����̎��ӂɂ�����s�X���𑣐i���邨���ꂪ�Ȃ��A���A�s�X�������ɂ����čs�����Ƃ�����͒������s�K���ƔF�߂�J���s�ׁi��14���j
(6)�@�W���n�搮���@��T���P���́A�W���n��̓y�n�̋��ŁA�c�_�����ƒ��a�̂Ƃꂽ�ǍD�ȋ��Z���̊m�ۂƓK���ȓy�n���p��}�邽�߁A���Y�W���n��̓����ɂӂ��킵�������y�ѕۑS���s�����Ƃ��K�v�ƔF�߂�����̂ɂ��ẮA�s�s�v��ɏW���n��v����߂邱�Ƃ��ł���|�K�肵�Ă���B
4�@�s�s�v��^�p�w�j
(1)�@�s�s�v��^�p�w�j�i����12�N12��28���t���ݏȓs�v����92�����ݏȓs�s�ǒ��ʒm�B�Ȃ��A�ߘa�Q�N�X���V���t���s�v��80���ɂ������O�̂��́B�ȉ������B�j�́A�n�������@�i���a22�N�@����67���j��245���̂S�s�Z�p�I�ȏ����y�ъ������тɎ����̒�o�̗v���t�̋K��Ɋ�Â��s���Z�p�I�ȏ����̐��i��L������̂ł���A���̎�|�́A���Ƃ��āA����A�s�s�����i�߂Ă�����œs�s�v�搧�x���ǂ̂悤�ɉ^�p���Ă������Ƃ��]�܂����ƍl���Ă��邩�A�܂��A���̋�̂̉^�p���e���x�̎�|���炵�āA�ǂ̂悤�ȍl�����̉��łȂ���邱�Ƃ�z�肵�Ă��邩���ɂ��Ă̌����I�ȍl�����������A�e�n�������c�̂Ɋ��p���Ă��炢�����Ƃ̍l���Ɋ�Â��Ē�߂���̂Ƃ��Ă���B
(2)�@�s�s�v��^�p�w�j�̇W�|�Q�s�s�s�v��̓��e�t�̂P�s�y�n���p�t�̇U�s�ʂ̎����t�̂f�s�n��v��t�ɂ́A�n��v�搧�x�̊��p�̗�Ƃ��āA�u�s�X���������ɂ����Ď��ӂɂ�����x�̌����{�ݓ�����������Ă���A�ǍD�ȋ��Z�����m�ۂ��邱�Ƃ��\�Ȓn��ŁA��Ƃ肠��ΖL���ȍx�O�^�Z��p�n�Ƃ��Đ������s���ꍇ�v���f���Ă���B
(3)�@�s�s�v��^�p�w�j�̇W�|�Q�̂P�̇U�̂g�s�h�ЊX�搮���n��v�擙�t�̂S�s�W���n��v��t�ɂ́A�W���n��v��́A�c�_�����ƒ��a�̂Ƃꂽ�ǍD�ȋ��Z���̊m�ۂƓK���ȓy�n���p��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���A��{�I�ȍl�����Ƃ��āA�W���n��v��̋��ɂ��ẮA�ǍD�ȋ��Z���̐����A���F����ƕ��݂̈ێ��E�ۑS�����Y�v��̍���̖ړI�ɉ����āA���Y���̐����y�ѕۑS����̂Ƃ��čs���ׂ��y�n�̋��Ƃ��Ē�߂邱�ƂƂ��Ă���B�܂��A�W���n��v��̋��ɂ́A�����Ƃ��āA�u���ɉƉ����A����n��ł܂Ƃ܂�̂����c�̓y�n�̋�擙���܂߂���̂ł���v�Ƃ��Ă���B
5�@�J�������x�^�p�w�j
(1)�@�J�������x�^�p�w�j�i����26�N�W���P���t���s�v��67�����y��ʏȓs�s�ǒ��ʒm�B�Ȃ��A�ߘa�Q�N�X���V���t���s�v��85���ɂ������O�̂��́B�ȉ������B�j�́A�n�������@��245���̂S�̋K��Ɋ�Â��s���Z�p�I�ȏ����̐��i��L������̂ł���A�J�������x���^�p���Ă����ۂ̋Z�p�I�����Ƃ��āA�s�s�v��^�p�w�j�Ɋ�Â��Ē�߂���̂Ƃ��Ă���B
(2)�@�J�������x�^�p�w�j�̇T�s�ʓI�����t�̂U�s�@��34���W�i��14���ȊO�j�t�̂W�s��11���W�t�́A�s�s�v��@��34���11���̋K��́A�s�X�����ɗאږ��͋ߐڂ��A���R�I�Љ�I�����������̓I�ȓ��퐶�������\�����Ă���ƔF�߂��A���A�����ނ�50�ˈȏ�̌��z�����A���Ă�����́A���ɑ������x�����{�݂���������Ă���A���́A�אځA�ߐڂ���s�X�����̌����{�݂̗��p���\�ł��邱�Ƃ���J���s�ׂ��s��ꂽ�Ƃ��Ă��A�ϋɓI�Ȍ��������͕K�������K�v�Ƃ���Ȃ��Ƃ̍l���Ő݂���ꂽ���̂ł���A�܂��A���̐ݒ�ɂ����Ă͎s�X�����ɗאږ��͋ߐڂ��Ă��邱�ƁA���R�I�Љ�I�����������̓I�ȓ��퐶�������\�����Ă���ƔF�߂��邱�ƁA�����ނ�50�ˈȏ�̌��z�����A���Ă��邱�ƁA�����̗v���S�Ă�������ݒ肷��K�v������A�����ꂩ�̗v���݂̂��������̋��ݒ�͍s�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ��Ă���B
(3)�@�J�������x�^�p�w�j�̇T�̂U�̂X�s��12���W�t�́A�s�s�v��@��34���12���̋K��́A�����14�������̊J���ɌW��J���R����̐R����̂�����^�I�Ȃ��̂͌�����ቻ���邱�Ƃ��\�ł���A���ɂ��J���s�ׂɌW����A�ړI�A�\�茚�z�����̗p�r�̑g�����Œ�߂邱�Ƃɂ��A�J������̖��m���ƊJ�����葱�̐v�����A�ȑf���Ɏ�������̂ł���Ƃ��Ă���B
(4)�@�J�������x�^�p�w�j�̇T�̂V�s�@��34���14�����W�t�̂P�s�s�X���������ɂ�����@��34���14�����̉^�p�t�ɂ́A�s�s�v��@��34���14���̋K��́A�����P�������13���܂łɊY�����Ȃ��J���s�ׂɂ��āA�n��̓����A�Љ�o�ς̔��W�̕ω��������Ă��A���Y�J���s�ׂ̗\�茚�z�����̗p�r�A�ړI�A�ʒu�A�K�͓����ʋ�̓I�Ɍ������āA���͂̎s�X���𑣐i���邨���ꂪ�Ȃ��A���A�s�X�������ōs�����Ƃ�����͒������s�K���ƔF�߂���ꍇ�́A�����14���Ɋ�Â��ċ����Ă������x���Ȃ��Ƃ��Ă���B�܂��A�ʏ�A�����Ƃ��ċ����č����x���Ȃ����̂ƍl��������̂Ƃ��āA���Ƃɔ����Z��A���p�Ώێ��Ƃ̎{�s�ɂ��ړ]���A�Ў����t�A�����{�݁i�����Ώۂ��s�X���������ɑ��݂��邱�Ɠ��̗��R�ɂ����́j���̌��z���̗p�ɋ�����J���s�ׂ��f���Ă���B
6�@�m�s�J���s�ד��Ɋւ����ᓙ
(1)�@�m�s�J���s�ד��Ɋւ�����i����12�N�R��27���t����77���B�ȉ��u�s���v�Ƃ����B�j�̕���28�N�R��28���t����23�������O�i�ȉ��u����28�N�����O�s���v�Ƃ����B�j�̑�16���̂S��P���́A�s�s�v��@��34���12���ɋK�肷����ŋ��A�ړI���͗\�茚�z�����̗p�r�������߂�J���s�ׂ́A�����ʕ\��Q�Ɍf��������ɂ����āA���\�ɒ�߂�p�r�̌��z�������z����ړI�ōs���J���s�ׂŁA�K���Œ�߂��ɓK�����Ă�����̂Ƃ���|��߂Ă���B
�����āA����28�N�����O�s���ʕ\��Q�́A�s�s�v��@��34���12���ɋK�肷����Œ�߂���Ƃ��āA���������̓��H�[���痼���e100���[�g���̋��i�ȉ��u���������������v�Ƃ����B�j���f���A�܂��A�����ɋK�肷����Œ�߂�p�r�Ƃ��āA�X�܁A�������A�q�ɂ��̑������ɗނ���p�r�ɋ����錚�z�������f���Ă���B
(2)�@�ߘa�R�N12��17���t����43�������O�̎s���i�ȉ��u�ߘa�R�N�����O�s���v�Ƃ����B�j��16���̂S��P���́A�s�s�v��@��34���12���ɋK�肷����ŋ��A�ړI���͗\�茚�z�����̗p�r�������߂�J���s�ׂ́A�ߘa�R�N�����O�s���ʕ\��P��T���Ɍf��������ɂ����āA���\�ɒ�߂�p�r�̌��z�������z����ړI�ōs���J���s�ׂŁA�K���Œ�߂��ɓK�����Ă�����̂Ƃ���|��߂Ă���B
�����āA�ߘa�R�N�����O�s���ʕ\��P��T���́A�s�s�v��@��34���12���ɋK�肷����Œ�߂���Ƃ��āA�s�X���������ł����āA�����ނ�300���[�g���ȓ��ɂl�s������������{�݂���������i�ȉ��u����W�����v�Ƃ����B�j�ŁA���A��n�Ƃ��ė��p���邱�Ƃ��K���ł�����̂Ƃ��ċK���Œ�߂�y�n�̋�擙�͈͓̔��̋����f���A�܂��A�����ɋK�肷����Œ�߂�p�r�Ƃ��āA�Z��A���Ȃ̎������A��Ə��A�q�ɂ��̑������ɗނ���p�r�ɋ����錚�z�������f���Ă���B
�Ȃ��A��L(1)�̕���28�N�����O�s����16���̂S��P���́A�ߘa�R�N�����O�s���ɂ����ẮA��16���̂S��Q���ɌJ�艺�����Ă���B�܂��A�ߘa�R�N�����O�s���ʕ\��Q�́A�s�s�v��@��34���12���ɋK�肷����Œ�߂���Ƃ��āA���������̓��H�[���猴��100���[�g���̋����f���Ă���B
(3)�@��L(2)�̂l�s������������{�݂́A�p�ۈ珊�A�o���w�Z�A�q�x���A�r�c�t�����Ƃ���|��߂��Ă���i����29�N�S���P��������131���j�B
