審理と裁決
国税不服審判所は、審査請求人の審理手続上の諸権利を十分尊重するとともに、審査請求人と原処分庁の各主張の間で争いのある点を中心に調査及び審理を行っています。
また、公正妥当な結論を得るため、合議制を採用するなど司法的原理も導入しています。
審理の流れ
審査請求書が提出された後の一般的な審理の流れは、次のようになっています。
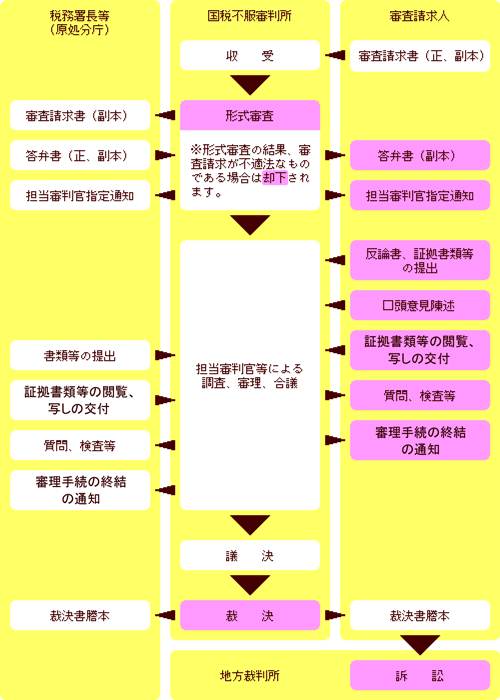
図内の「形式審査」「却下」「答弁書(副本)」「担当審判官指定通知」「反論書、証拠書類等の提出」「口頭意見陳述」「証拠書類等の閲覧、写しの交付」「質問、検査等」「審理手続の終結の通知」「裁決」「訴訟」をクリックするとその説明に移動します。
形式審査と記載内容の補正等
国税不服審判所では、審査請求書が提出されると、まず、その審査請求が法律の規定に従っているか否かについて形式的な審査を行います。
その結果、審査請求書に記載漏れ等の不備があるときは補正を求めることがありますし、また、審査請求の趣旨、理由を計数的に説明できる資料の添付を求めることもあります。
具体的には、次のようなケースについて補正を求めます。
- 審査請求書が正副2通提出されていないもの
- 審査請求書に必要事項の記載がないもの
- 審査請求に係る処分の内容が特定されていないもの
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日(その処分に係る通知を受けた場合には、その通知を受けた年月日)が適切に記載されていないもの
- 再調査の請求についての決定を経た後の処分について審査請求する場合に、再調査決定書の謄本の送達を受けた年月日が適切に記載されていないもの
- 審査請求人の氏名(法人の場合は名称)、住所又は居所(法人の場合は所在地)等が適切に記載されていないもの
- 審査請求人の代表者、納税管理人若しくは代理人又は総代の氏名及び住所又は居所が適切に記載されていないもの
- 代理人又は総代が選任されているときに、その権限を証する書面の提出がないもの
- 代理人又は総代が選任されているときにその権限を証する書面(委任状、総代の選任届出書)の提出がないもの
審査請求書の提出後に代理人又は総代を選任した場合には、速やかにその権限を証明する書面(委任状又は総代選任届出書)を提出してください。
- 審査請求の趣旨及び理由の記載が不明確なもの
例えば、単に「原処分は違法であるからその全部の取消しを求める」と記載されているもの
※ 審査請求の趣旨及び理由の記載に当たっては、処分の取消し又は変更を求める範囲を明らかにするとともに、処分の理由に対する主張が明らかになるように記載してください。
- その他、以下に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる事項の記載がないもの
- 再調査の請求をした日の翌日から起算して3か月を経過してもその再調査の請求についての決定がないことにより、再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合・・・再調査の請求をした年月日
- 再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由があることにより、再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合・・・その正当な理由
- 不服申立期間※を経過した後において審査請求をする場合・・・不服申立期間を経過したことについての正当な理由
※ 不服申立期間- 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(処分のあった日の翌日から起算して1年を限度とする。)
- 再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内
却下の裁決
審査請求の形式審査の結果、期間を定めて不備を補正するよう求めたにもかかわらず、審査請求人が補正しない場合や、審査請求書が法定の審査請求期間経過後に提出された場合など不適法な審査請求であって補正することができないことが明らかなときには、国税不服審判所長は、審理手続を経ずに、審査請求を「却下」する裁決を行い、これを裁決書謄本により審査請求人に通知します。
なお、例えば、審査請求が法定の審査請求期間経過後になされた場合であっても、正当な理由があるか否かを審理しなければ、その審査請求が不適法なものかどうか明らかにならないような場合などには、審理手続を経た上で却下すべきかどうかを判断することとなります。
審査請求が却下されるのは、次のような場合です。
- 審査請求の対象が処分でないとき
例えば、延滞税のお知らせなど、処分に該当しないものを審査請求の対象としたとき
- 審査請求の対象が審査請求をすることができない処分であるとき
例えば、その審査請求が、再調査の請求についての決定の取消しを求めるものであるとき
- 審査請求の対象となった処分が存在しないとき
例えば、審査請求の対象とされた処分がはじめから存在しないとき

審査請求の対象とした処分が、裁決前に消滅したときも却下されます。
- 審査請求の対象となった処分が審査請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものでないとき
例えば、納税額を減少する更正処分(更正の請求についてその一部を認める更正処分を除く。)を審査請求の対象としたとき
- 審査請求の対象となった処分について、既に国税不服審判所長の裁決(却下の裁決を除く。)がされているとき
- 審査請求人が行った再調査の請求が不適法であるとき
例えば、再調査の請求が法定の再調査の請求期間経過後になされたことを理由として却下されたものについて、審査請求をしたとき
- 審査請求が正当な理由なく法定の審査請求期間経過後にされたとき
- 審査請求の対象となった処分について、審査請求人が直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者でないとき
- 不適法な審査請求について相当の期間を定めて補正要求がされた場合において、当該期間内に補正されなかったとき
答弁書の送付
形式審査の結果、適法な審査請求であると認められる場合や、適法な審査請求かどうかの判断に審理を要すると認められる場合には、原処分庁に対して「答弁書」の提出を求めます。
この答弁書には、審査請求の趣旨及び理由に対応して、原処分庁の主張を記載しなければならないことになっています。
具体的には、審査請求の趣旨に対応して、いかなる内容の裁決を求めるかが明らかにされるとともに、審査請求の理由により特定された事項に対応して、原処分庁の主張が具体的に記載されます。
国税不服審判所長は、原処分庁から提出された答弁書の副本を審査請求人に送付します。
担当審判官等の指定の通知
国税不服審判所長は、審査請求に係る調査及び審理を行わせるため、担当審判官1名及び参加審判官2名以上を指定します。
指定された担当審判官は、参加審判官とともに合議体を構成し、その合議によりその審査請求の調査及び審理を進めることとなります。
国税不服審判所長は、指定した担当審判官及び参加審判官等の氏名及び所属等を書面で審査請求人に通知しますので、審査請求人は、担当審判官に対して具体的な主張、立証等を行うこととなります。
例えば、主張の追加及び変更、反論書及び証拠書類等の提出、口頭意見陳述の申立て、証拠書類等の閲覧・写しの交付の請求等は、担当審判官に対して行うこととなります。
審理手続における相互協力
審理関係人(審査請求人、参加人及び原処分庁)及び担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならないとされています。
審理手続の計画的遂行
担当審判官は、審査請求に係る事件が、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど複雑である場合などにおいて、審理手続(口頭意見陳述、証拠書類等の提出及び審理のための質問・検査等)を計画的に遂行する必要があると認めるときには、審理関係人を招集して、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見聴取を行うことがあります。
これは、審査請求に係る審理を迅速かつ公正に行うことを目的として行われるものです。
反論書・証拠書類等の提出
審査請求人は、送付された原処分庁の答弁書に対する反論を記載した反論書を提出することや自らの主張を裏付ける証拠書類等を提出することができます。
この場合、担当審判官が提出すべき期間を指定したときは、その期間内にこれらを提出しなければならないこととされています。
また、原処分庁も処分の理由となった証拠書類等や審査請求人の反論書に対する意見を記載した意見書を提出することができます。
※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。
口頭意見陳述の申立て
審査請求人は、自らの主張を書面で提出するほか、口頭で意見を述べることができます。
担当審判官は、審査請求人から口頭意見陳述の申立てがあった場合には、原則として、その機会を与えなければならないこととされています。
担当審判官は、口頭意見陳述の機会を設ける場合には、期日、場所を指定して審査請求人に通知するとともに、原処分庁の担当者にも原則として出席を求めます。
審査請求人は、担当審判官の許可を得て、補佐人とともに出頭することができます。補佐人とは、審査請求人に付き添って口頭意見陳述の期日に出頭し、その陳述を補佐する者をいいます。
審査請求人は、口頭意見陳述の際には、口頭で意見を述べることができるとともに、担当審判官の許可を得た上で、原処分庁の担当者に質問をすることができます。なお、質問が審査請求に関係がない事項にわたる場合や既にされた質問の繰り返しにすぎない場合などには、質問を許可しない場合があります。
※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。
- リーフレット「口頭意見陳述の申立てをされる方へ」[ PDF ]
閲覧・写しの交付の請求
審査請求人は、原処分庁から担当審判官に提出された処分の理由となった証拠書類等や、担当審判官が原処分庁等から調査により提出を受けた資料等の閲覧を求めることができることに加え、それらの写しの交付を求めることもできます。また、原処分庁も、審査請求人が提出した証拠書類等や、担当審判官が調査により収集した資料等の閲覧・写しの交付を求めることができます。
担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧・写しの交付の請求を拒否できないことになっています。
担当審判官は閲覧を実施する場合には日時、場所について、書面で審査請求人等に通知します。
※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。
- リーフレット「証拠書類等の閲覧・写しの交付請求をされる方へ」[ PDF ]
写しの交付には、用紙1枚につき10円の手数料がかかり、収入印紙で納付していただくことになります。
なお、証拠書類等の写しの交付に代えて、閲覧請求人等が持参したカメラで撮影することもできます。その場合には手数料はかかりませんが、庁舎管理上の問題などで撮影が認められない場合もあります。
担当審判官等による質問、検査等
調査及び審理に当たっては、審査請求人及び原処分庁から証拠書類等が積極的に提出される必要がありますが、提出された証拠書類等のみでは事実解明に不十分な場合もあり、また、当事者から提出された証拠書類等の中には確認のための調査を必要とするものもあります。
このように審理を行うため必要があるときは、担当審判官は、審査請求人・原処分庁の申立てにより又は職権で質問、検査等を行います。
具体的には、次に掲げる行為をすることができます。
- 審査請求人若しくは原処分庁又は関係人その他の参考人に質問すること
- 上記1の者の帳簿書類その他の物件について、その所有者、所持者若しくは保管者に対し、その物件の提出を求めること又はこれらの者が提出した物件を留め置くこと
- 上記1の者の帳簿書類その他の物件を検査すること
- 鑑定人に鑑定させること
なお、担当審判官以外の国税不服審判所の職員は、担当審判官の嘱託、又はその命を受けて上記1及び3の行為をすることができることとなっています。
※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。
調査及び審理の保留
審査請求の対象とされた処分が、査察事件、行政訴訟事件及び民事事件等に密接に関係するものについては、例えば次のような理由により、調査及び審理を一時見合わせることがあります。
- 調査及び審理の段階において、原処分庁及び審査請求人の手元に関係書類が存在しない場合
- 原処分の適否につき又は当事者間の紛争が、現に裁判所に係属しているなどの事情がある場合
審理手続の終結
担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結し、審査請求人及び原処分庁にその旨を文書で通知します。
担当審判官が、審理手続を終結すると、審査請求人及び原処分庁は、例えば次の行為をすることができなくなります。
- 答弁書の提出
- 反論書の提出
- 口頭意見陳述の申立て
- 証拠書類等の提出
- 担当審判官に対する質問、検査の申立て
- 閲覧・写しの交付の請求
- 主張の追加、変更又は撤回
裁決
調査及び審理が終了すると、合議体を構成する担当審判官と参加審判官との合議により議決が行われます。合議において構成員は、それぞれ独立した立場で十分意見を述べ合い、公正妥当な結論に到達するよう議論を尽くし、最終的には、その構成員の過半数の意見により議決を行います。
議決がされると、国税不服審判所長は、合議体の議決に基づいて裁決を行います。
また、原処分以上に審査請求人に不利益となるような裁決はできないことになっています。
裁決の内容は、「裁決書謄本」により審査請求人と原処分庁の双方に通知されます。
1. 裁決の態様
A. 全部取消し
審査請求人が原処分の全部の取消しを求める場合において、その主張の全部を認めたときにする裁決
B. 一部取消し
審査請求人が原処分の全部の取消しを求める場合において、その主張の一部を認めたとき、又は、審査請求人が原処分の一部の取消しを求める場合において、その主張の全部又は一部を認めたときにする裁決
C. 変更
審査請求人が原処分の変更を求める場合において、その主張の全部又は一部を認めたときにする裁決
例えば、次に掲げる処分についての変更がこれに当たります。
- 耐用年数の短縮に関する処分
- 特別修繕準備金に関する処分
- 相続税額及び贈与税額の延納条件に関する処分
- 納税の猶予に関する処分
D. 棄却
審査請求人が原処分の取消し又は変更を求める場合において、その主張を認めなかったときにする裁決
裁決には、上記のほか、審査請求が法定の不服申立期間経過後にされたものである場合その他不適法であるときにされる「却下」があります。詳細は、前述の『却下の裁決』を参照してください。
2. 裁決の拘束力
裁決は、関係行政庁を拘束するので、原処分庁は裁決に不服があっても訴えを提起することができません。
訴訟
審査請求人は、裁決の結果、なお不服がある場合には、裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に裁判所に訴えを提起することができます。
また、審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がされないときは、裁決を経ないで訴えを提起することができます。この場合、訴訟とは別に、引き続き国税不服審判所長の裁決を求めることもできます。
